
Doll & Photo : Mahoko Akiyama
後期韻文詩編

Doll & Photo : Mahoko Akiyama
菩提樹の、輝く若葉に
病的な勝鬨が死んでゆく。
だが、精神のシャンソンは
スグリの実の間を旗めく。
我らが血よ、血管中で笑ってくれ、
そら、ブドウの蔓も絡み合う。
空は天使のように清らかだ
青空と波は、心を通わす。
さあ、行くぞ。もしも、光がぼくを傷つけたら
苔の上で死んでやる。
みんな、辛抱して、うんざりして
それは、たやすいことさ。苦労なんか糞食らえ。
ドラマチックな夏の、幸運の車輪に
ぼくは縛り付けられたいのだ。
おまえにしっかり抱かれて、おお、自然よ、
―少しは孤独でもなく虚しくもなく ! ―ぼくは死ぬんだ。
だが、おかしなことに、「羊飼いたち」は、
世間の手に落ち、死ぬばかり。
季節よ、ぼくをすり減らしてくれ。
「自然」よ、おまえの下に、ぼくは帰る;
飢えと、すべての渇きも、一緒だ。
だから、お願いだ、食わせてくれ、飲ませてくれ。
ぼくに、迷わせるものは、何もない;
太陽に笑うことは、両親に笑うことだ、
だが、このぼくは、誰にも笑いたくない;
そして、自由とは、この不運のことなんだ。
1872年5月
フランス語テキスト

Doll & Photo : Mahoko Akiyama
あらゆることに縛られて
虚しく過ぎる青春よ、
気が弱いばっかりに
おれは人生を失った。
ああ! 心と心の求め合う
あの時が来てはくれないか。
おれは自分に言った:放っておけ、
で、誰もおまえを見ないよう:
で、最も高い歓びの
約束がない限り。
誰にも止められないように
厳しく引退するのだ。
絶対忘れられぬほど
おれはこんなに我慢した;
恐れと苦しみが手をとって
天の彼方に飛んでった。
そして病的な渇きが
おれの静脈を暗くした。
こうして「あの草原」は
忘れ去られて捨てられて;
お香ばかりか、毒麦までも
茂り放題、花盛り、
不潔なハエが100匹も
獰猛な羽音を立てている。
ああ! 限りないやもめ暮らしの
こんなあわれな魂に
思い浮かぶは
聖母様の姿だけ!
処女マリアにお祈りすれば
よろしいのでございましょうか?
あらゆることに縛られて
虚しく過ぎる青春よ
気が弱いばっかりに
おれは人生を失った。
ああ! 心と心の求め合う
あの時が来てはくれないか!
1872年5月
フランス語テキスト
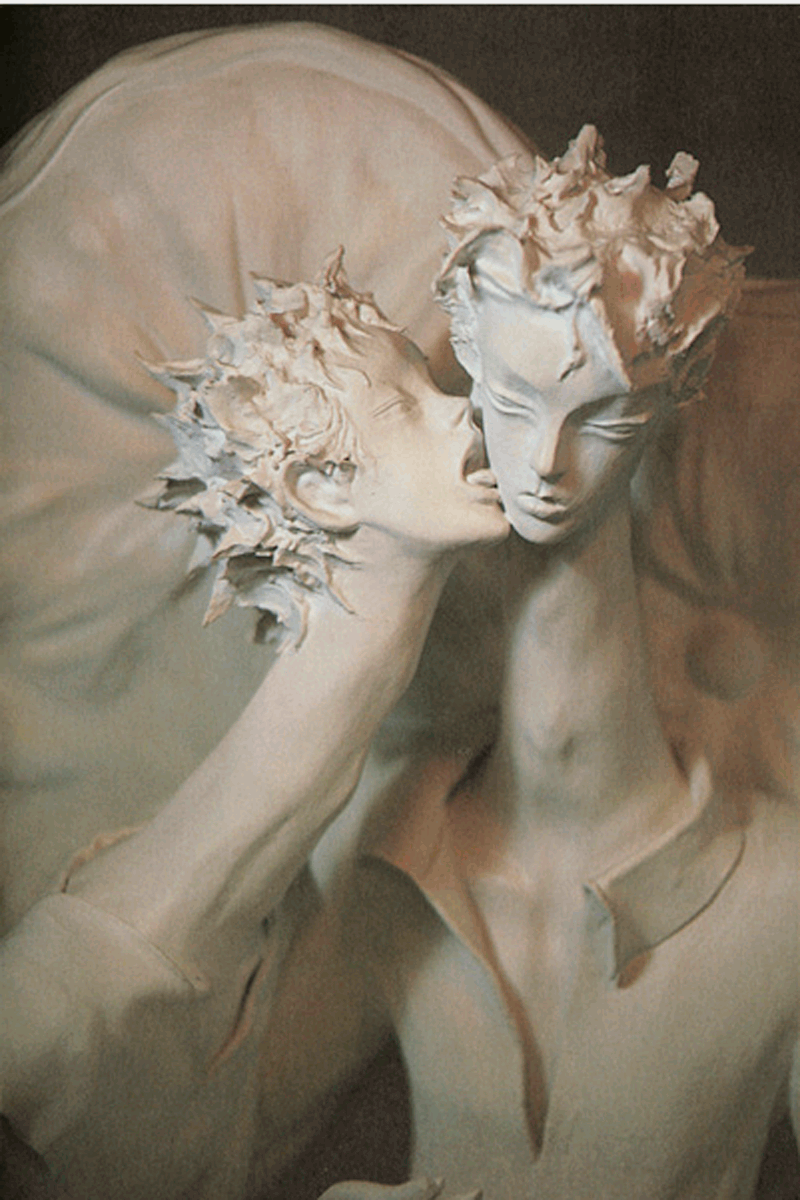
Doll & Photo : Mahoko Akiyama
見つかった。
何が?―「永遠」。
太陽と一緒に
行ってしまった海。
見張り番の魂よ、
孤独な夜と
火と燃える昼の
告白をつぶやこう。
みんなの賛同からも、
ちまたの熱狂からも
おまえは自由になって
あれのままに飛んで行く。
そうさ、サテンの燠火たちよ、
おまえたちだけから、
あの「お務め」がわき上がる
おしまい:なんて言われずに。
希望なんかあるもんか、
救われたりもするもんか。
辛抱強く修行をしても、
刑罰だけが確実だ。
見つかった。
何が?―永遠。
太陽と一緒に
行ってしまった海。
1872年5月
フランス語テキスト
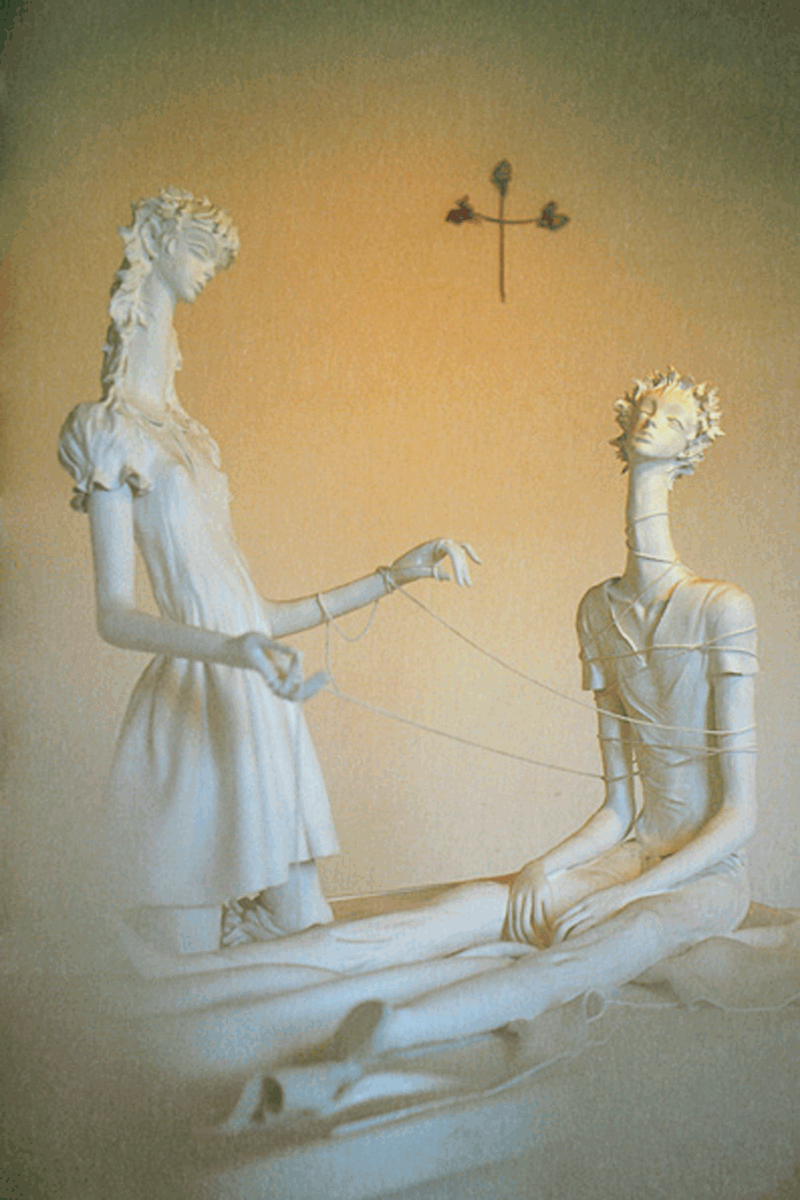
Doll & Photo : Mahoko Akiyama
ある声が
いつも天使ぶって
―おれのことを、―
手厳しくお説教。
いちいち小うるさい
あれやこれやの詰問も
とどのつまりはなるだけさ、
酔いどれと乱痴気騒ぎに;
このお囃子で行きましょう
楽しすぎる、簡単すぎる;
波と、草花とがあるばかり、
そいつがお前の家族だぞ!
すると、あの声も歌い出す、おお
楽しすぎる、簡単すぎる、
そして、はだかの目にもよく見える…
―おれもあの声と一緒に歌う、―
このお囃子で行きましょう
楽しすぎる、簡単すぎる、
波と、草花とがあるばかり、
そいつがお前の家族だぞ!… とかなんとか…
するとある声が
―天使ぶって!―
おれのことを、
手厳しくお説教;
そして、一気に歌う、
吐く息と一緒に;
ドイツ口調で、
だが、激しくめいっぱいで:
世間は堕落してるんだ;
おまえが驚くなんてもんじゃないぞ!
生きて火にくべるんだ
訳の分からない不幸を。
おお! 美しい城よ!
おまえの生涯はなんて清らかなんだ!
おまえは「いくつ」なんだ
王様の自然の
おれたちの兄貴よ? とかなんとか…
おれも一緒に歌おう:
たくさんのシスターよ! 声は
世には全く知られてないが!
おれをつつんでくれ
つつましい栄光で。とかなんとか…
1872年6月
フランス語テキスト
翻訳:門司 邦雄
掲載:1998年5月1日、1999年5月、2001年1月28日、
2002年3月30日、2006年5月20日、2006年6月29日、
2016年2月3日、2020年12月11日
ランボーの「永遠」
この詩には日付が付けられていて、「五月の軍旗」「最も高い「塔」の歌」「「永遠」」は1872年5月、「黄金時代」は同年6月と記されています。「「永遠」」は単独でさまざまな解釈がなされています。「最も高い「塔」の歌」も、ランボー自らが「歌」(シャンソン)と書いたように、その音楽性から人気のある詩です。この2つの詩は『地獄での一季節(地獄の季節)』の「錯乱 II 言葉の錬金術」に、アレンジし直されて引用されています。「黄金時代」は草稿では「「永遠」」のすぐ後に引用する予定でしたが、決定稿には引用されませんでした。手書き原稿写真版を見ると、番号が付された小タイトルが始めに列記されていて、その後、番号無しの小タイトルの付いた各詩が書かれています。
ここでは『地獄での一季節』に引用され、ランボー自らがより抽象的、象徴的に書き直した詩ではなく、番号が振られた4編の詩として読んでみました。内容的に、「五月の軍旗」は、再びパリに出てきたランボーの決意を歌ったものです。「最も高い「塔」の歌」はヴェルレーヌと離別していたときの心情、そして「「永遠」」はヴェルレーヌとの愛の絶頂、「黄金時代」はシャルルヴィルでの母親の小言のパロディです。これらの韻文詩は、詩の音楽性を重視したヴェルレーヌの影響下に書かれたものと思われます。
「我慢の祭」の4篇の詩は時の流れとは反対に書かれていると考えられます。1871年9月ランボーはヴェルレーヌの招きでパリに出てきます。やがて、ランボーとヴェルレーヌは同性愛関係になりました。ヴェルレーヌは妻マチルドから離婚を請求され、1872年2月ランボーは故郷シャルルヴィルに戻されます。しかし、1872年5月中旬、ランボーは再びパリに来てヴェルレーヌと再会します。(詳しくは年譜を参照してください)
「黄金時代」はヴェルレーヌと出会う前のシャルルヴィルでのランボーの精神生活を、「「永遠」」はランボーとヴェルレーヌの同性愛を、「最も高い「塔」の歌」はシャルルヴィルに再び戻されたランボーの心情を、そして「五月の軍旗」は再びパリに出てきたランボーの心情を詠んだものと思われます。ここで、この詩は1871年のパリ・コミューンを生々しくよみがえらせます。なぜ、ランボーが逆順に詩を書いたか(少なくとも「黄金時代」は、日付的に最後に来ます)、それはこの詩がヴェルレーヌに宛てられたからだと思います。1872年の春から初夏にかけて、ランボーは次々と新しい詩を試み、書いた時期です。この時のランボーには、詩の時空が現在にも未来にも過去にも開かれていたように見えたと思えます。ヴェルレーヌとの同性愛も含め、見える者の詩法が最も実践された時だったのでしょう。
タイトル「我慢の祭」は、性的欲望も含め、自分の欲望、欲情を我慢している状態を言っているのでしょう。ただし、「「永遠」」は充足の表現でもあるわけですが…。
「五月の軍旗」
再びパリに出てきたランボーの心情を詠んだ詩。
題名の「軍旗 bannières 」は、パリ・コミューンの旗(複数)、つまり血の赤旗を指しています。bannière は英語ではバナー( banner )で、横長の旗を意味します。ヤフー「フランス詩」トピに参加している gramporte2001 がジャンヌダルクの軍旗のページを紹介してくれました。向って右が十字架にかけられたキリストの描かれた bannière です。https://en.wikipedia.org/wiki/File:Joan_of_arc_miniature_graded.jpg
第1節は、2行単位で、明と暗、生と死が対比され、詩の音としても澄んだ音とくぐもった音が対比される構成となっています。たとえば、最初の2行では、光輝く春の若葉で始まります。しかし、その樹は死者を弔う菩提樹です。そして、その若葉に、狩人が獲物を追い詰めた「あらららら」という時の声( hallali )が消えてゆきます。声には病的なという形容詞が付き、「消えてゆく」は死ぬにあたる mourir が使われています。1871年の5月、つまりこの詩の書かれる1年前の5月、ペール・ラシェーズ墓地の「連盟兵の壁」で、コミューン兵士が銃殺されて、パリ・コミューンは終わります。この詩の最初のシーンは、パリ・コミューンの最期から始まっているように思えます。
私は、ペール・ラシェーズ墓地には行ったことがないので、そこに菩提樹など、この詩に書かれた植物が実在する、または、していたかは分かりません。あるいは、ランボーがイメージとして菩提樹を使用したとも考えられます。壁の蔦がブドウになったのかも知れません。「フサスグリの実」と訳した groseilles は、「房スグリ」の小さな赤い実、あるいはその潅木のことです。今では英語の red currant (レッドカラント)の方が分かりやすいかも知れません。ブドウのように房になった小さな赤い実をつけます。白い実もあるそうです。フサスグリの赤い実はブドウを、赤ワインを、そして血を連想させます。湿度の低いヨーロッパでは、ワイン用のブドウは地面に立てた杭に這わせます。ブドウの枝を血管に見立てているのでしょう。そして絡み合うブドウの樹は、絡み合う肉体、つまり同性愛を暗示しています。「青空と波」の「波 onde 」は、人の波、つまりデモや集会での人の波の意味でしょう。新聞 Le Monde でこのように使われているのを見ました。
第2節には、「幸運の車」が出てきます。「幸運 fortune 」は、運命とも訳されますが、財産という意味もあります。この詩では、最終行の「不運(不幸) infortune 」と対になって使われていると思われます。「羊飼いたち Les Bergers 」 と定冠詞が付きで大文字で書かれていますが、羊飼いには恋人という意味合いがあり、世間の手で果てるこの恋人たちとは、ランボーとヴェルレーヌのことを暗示しているのでしょうか。世間や親から煩わされることなく自由に生きたいという、初期詩編からのランボーのテーマが繰り返されています。親に従いたくないという具体的な言葉は、ランボーとヴェルレーヌが「親たち」によって別れさせられたという意味なのでしょうか。しかし、この詩では初期詩編の「自然」は、帰るあてのない「死」という自然に変質しているように見えます。そして、自然の光の中で浄化されることと死が結び合わされています。この詩は、再びパリに出て来たランボーの、中断された見える者プロジェクト実現への意志を示していると読むこともできます。やがてランボーはマチルドからヴェルレーヌを奪い取ります。ランボー流に言うのであれば、ブルジョワへの帰属からヴェルレーヌを解放したということになるのでしょう。
「我慢の祭」は、ランボーからヴェルレーヌに送られた二通目のラブレター(一通目は「酔っぱらった船(酔いどれ船)」)だったのかも知れません。君がぼくを捨てるんだったら、一人で死ぬさ、という…。
なお、最後の行「自由とは、この不運のことなんだ。」は直訳すれば「そして、自由とはこの不運のことなんだろう。」となります。「自由」 soit 「この不運」と書かれています。動詞 soit は、(…で)あるという être (英語では be 動詞)の接続法現在形です。「あって欲しい」という願望に訳す翻訳者もいますが、私は単純に「該当する」という意味に取りました。「そして、自由とはこの不運に該当する。」と直訳できます。フランからユーロへの切替え時、インターネットのショッピングモールで、2,61EUR soit 17,12FF (2,61ユーロは17,12フランです)というふうに使われていました。
「最も高い「塔」の歌」
ヴェルレーヌと離別していたときの心情を詠んだ詩。
塔は、男性あるいは男性器をシンボライズした建造物であることは広く知られています。ストーン・サークル、そして、日本の門松も、中央の男性器とそれを取り巻くように形作られた女性器で、性交をあらわしているという説があります。また、ヨーロッパの都市で「最も高い塔」は、近代・現代の建築物が建つまでは教会の尖塔 flèche でした。ヴェルレーヌが別れているランボーに出した手紙に「十字架の道行き」という言葉が書かれていました。これは「刑罰だけが確実だ」という「3. 「永遠」」にも通じる言葉で、見える者の詩法だけでなく同性愛関係も暗示しています。
実際にランボーとヴェルレーヌが別れていた時期は冬から春なのですが、この詩のイメージは春から初夏を思わせます。第4節のハエの群れ飛ぶ草原は、初期詩編の「母音」の「A」の表現から来ていると思われます。最も高い歓びのために隠れているランボーは、女性(の性器)にも興味を失ったという意味なのでしょうか。この詩の表現は、「母音」とは異なり、仰向けに寝て股を開き両足を引き上げた(M字開脚の)裸の女性(の性器)のイメージと思われます。「お香 encens 」は、やはり宗教的な意味で、毒麦との対比も含めて使用された言葉だと思われます。encens を、「まんねんろう」つまりローズマリーとする翻訳もあります。私が調べた範囲では、特にローズマリーを意味する指摘は見つかりませんでした。ローズマリーの枝を香として使用することを意味しているのかは分かりません。香草、つまり薬効も含めてハーブを意味していると解釈することも可能かも知れませんが、ここではランボーが初期詩編から書いている(若い)女性とキリスト教の関係を暗示して、教会内で焚かれる「香」をイメージしていると思います。ランボーにとって良い香りという意味で使われたのではないでしょう。毒麦 ivraies にも宗教的な比喩として聖書で使われています。続く第5節も、キリスト教と女性に対する皮肉なのでしょう。「聖母様」「処女マリア」は、当時フランスで流行していたルルドの泉のマリア詣でを連想させます。「処女マリア」にお祈りすれば、性の飢えが癒されるのでしょうかという皮肉を、少し回りくどい口語的な言い回しの Est-ce que (…ですか)で表現したように思えます。(詳しくは、初期詩編の「母音」を参照してください)
この詩は、次の「3. 「永遠」」とともに、『地獄での一季節』の「錯乱 II 言葉の錬金術」にかなりアレンジされて引用されています。「「永遠」」が、元の形を多く残しているのに比べ、この詩は「我慢の祭」での意味合いから離れ、より象徴的な表現となっています。
「「永遠」」
後記韻文詩編中、最も有名な詩です。5音綴の韻文詩で、ランボーとヴェルレーヌとの愛(同性愛)の絶頂(オルガスム)を詠んだ詩。「永遠」は、背徳の同性愛の一瞬の絶頂にあり、社会あるいは神の中には、つまり季節の上には存在しないという詩だと思います。なお、やはり後期韻文詩編にある「(おお、季節よ…)」は、この詩のテーマをより認識的に書いています。
この詩の第1節は、詩人ランボーの代表的イメージとなっていると言えるでしょう。特に、ジャン-リュック・ゴダール Jean-luc Godard 監督の映画「気狂いピエロ Pierrot le fou 1965」に引用されたことが大きいと思います。日本語訳としては、『地獄での一季節』の「錯乱 II 言葉の錬金術」の「太陽に混ざった」「太陽に溶けた」「太陽にとろけた」などの方が知られています。この表現の方が、金赤色の夕日が太洋ににじんだイメージを連想させて、イメージが見えやすいからでしょう。
ここに翻訳した詩は、ポショテク版(1999)をテキストにしています。この詩にもヴァリアント(別ヴァージョン)がありますが、「錯乱 II 言葉の錬金術」に引用されたヴァリアントとの中間にあたるように思われます。タイトル「「永遠」」の「永遠 L'Éternité 」は、「我慢の祭」の詩の中で唯一定冠詞が付けられ、さらに第1節の「「永遠 L'Éternité 」」も定冠詞が付き、大文字で始まります。第6節の「永遠」は小文字で始まっています。この詩の「永遠」は特別の「「永遠」」で始まり、詩の思索の中でより象徴化、抽象化、あるいは概念化された「永遠」に変わります。なお、ヴァリアントには、タイトルの定冠詞も、自問自答を暗示する「―」も無く、第1節の「永遠」も小文字で始まります。
最初の行の「見つかった」ですが、これは女性形の名詞 elle 、ある物か人が(再び)見つかったという意味です。「また見つかった」とすると、「また」の意味が強すぎて、同種の違うものが何個も見つかるようにも取られてしまいます。何回か訳を変えてみましたが、無くしたものを探し出したとき、そのときの日本語は「…が見つかった」となり「また見つかった」とは言わないので、シンプルに「見つかった」としました。また、第6節を「また見つかった」ともしてみましたが、詩のリフレインが無くなってしまうという指摘があり、第6節も「見つかった」としました。第1節の4行は、倒置も無く、きわめてシンプルで日常的、言い換えればくどくない表現で、そこに非日常的なイメージを乗せていることが、この節の印象を劇的にしていると思います。最初の2行「見つかった。/何が?―「永遠」。」は、原文では、Elle est retrouvée. / Quoi? - L'Éternité. となり、発音は、エレェルトルヴェ。クワァ?―レテルニィテェとなります。音自体でも、オルガスムを表していると思います。
この詩の「「永遠」」は具体的な体験から始まりました。私は(も)、それは具体的に同性愛の射精のオルガスムとその直後の充足した虚脱感だと思います。引用した詩のタイトルからは定冠詞が取られ、「永遠」は小文字になり、抽象化されていきます。「太陽と一緒に/行ってしまった海」ではなく、「太陽と/混ざった海」に変わり、より象徴化されたイメージに変わります。「一緒に行く」は、aller avec です。これは、服が合うなどの意味もあり、話し言葉として「男女が交わる」という意味もあります。日本語でも、たとえば「うまく行く」という表現はさまざまな意味を持ちますし、オルガスムに到達することを「行く」といいますので、ここでは「行ってしまった」と訳しました。
ここに、錬金術的な思想、火と水の合体による錬金を見ることもできます。また、後期韻文詩編の「思い出」でも、水は女性を、太陽は男性を象徴しています。私は、ランボー自身が「酔っぱらった船」の第7節で書いたシーンを思いだします。金赤色の夕日が一面に映える(ムーズ川の)水面、それは短い時間ですが永遠を思わせる太陽と水の「愛」の時間でもあったと思います。
「突然、青海原を染めながら、太陽の
真っ赤な輝きの下で、アルコールより強烈な錯乱と、
ぼくらの竪琴より広大なゆったりとしたリズムで、
「海の詩」に、愛欲の苦い赤茶色の染みが発酵する!」
そして、少年ランボーは、その短い時間を、永遠のように、「長いこと夕日のもの寂しい黄金色の泡立ちを見ている」(『イリュミナスィオン』「少年時代 IV 」)のでしょう。ランボーは「「永遠」」を書いた時点では、まだ海を見ていません。ムーズ川でのボート遊びや文学、あるいは絵画から、象徴化された海をイメージしたのでしょう。
第4節目の「サテンの燠火たち」(燠ではイメージが取りにくいので火を付けました)は、もちろんランボーとヴェルレーヌのことでしょう。サテン satin は発音はサタンで、悪魔 satan の発音に、全く同じではありませんが鼻音で似ています。この表現は、たとえば『イリュミナスィオン』の「野蛮な」の「燃えさかる燠火と泡立ち」に受け継がれます。「燠火」は充血した性器(あるいは肛門)、「泡立ち écumes 」は精液と読むこともできるでしょう。ポール・エリュアールは「二人の夜 Nuits Partagees 」で「泡立ち écume 」 を女性の体液の意味に使っています。
「救われたりもするもんか」と意訳した Nul (無い) orietur の orietur は、ラテン語で、ブリュネルの注では se lever (立ち上がる、昇る)という意味と解説されています。また、L. フォレスティエがこの部分を「夜明けは無い」と訳したことを紹介しています。しかし、むしろ宗教性から orietur の引用元として旧約聖書のマラキ書第4章(現在では第3章)20節を参照例として示しています。託宣の意味が解るように「主の日」の見出し以下、19節と20節をここに引用します。「(19)見よ、その日が来る/炉のように燃える日が。高慢な者、悪を行うものは/すべてわらのようになる。/到来するその日は、と万軍の主は言われる。/彼らを燃え上がらせ、根も枝もない。/(20)しかし、わが名を畏れ敬うあなたたちには/義の太陽が昇る/その翼にはいやす力がある。/あなたたとは牛舎の子牛のように/踊りで出て跳び回る。」(新共同訳聖書)と書かれていて、最後の審判の日を予言しています。また、第23節には、審判の日の前に預言者エリアを遣わすと書かれています。20節の「昇る」にあたる部分が orietur です。最後の審判による救済という意味をランボーが暗示したと考え、「救い」と意訳しました。
「永遠」のもうひとつの読みとして、la mer (海)が、同音の言葉 la mère (母)を暗示していると言われています。「永遠」は、幼児の母親との一体感の記憶なのでしょう。同じ後期韻文詩編の「思い出」のように、太陽は夫、父であり、海(「思い出」では川)が母です。『イリュミナスィオン』の「少年時代 II 」の中にも「若くして亡くなった母親( maman )」が出てきます。ランボーの父は、ランボーが6歳になる少し前に完全に別居、これが母の厳格な(宗教)教育の一因と言われています。夫に去られた母ヴィタリーは、キリスト教(カトリック)への信仰をさらに強くしますが、このことが母をキリストに取られたという思いを幼いランボーに抱かせたと思われます。いわゆる優しい母の思い出がランボーの中ではここで途切れている、つまり父が去ると、母も去っていたとイメージされていたのかも知れません。
「黄金時代」
母親とランボーの関係をパロディックに描いた詩。
自然に囲まれ、母親に管理されたシャルルヴィルでのランボーの精神生活を、ちょっとおどけた感じの詩、今風に言えば「詞」にした作品です。「このお囃子で行きましょう/楽しすぎる、簡単すぎる;/波と、草花とがあるばかり、/そいつがお前の家族だぞ!」の部分は、前の節の「乱痴気騒ぎ folie 」の内容と考えられます。「お囃子」と訳したところ tour で、英語なら turn 、ひと巡りとか回転という意味です。自転車レースのツールドフランスのツールです。この意味から、業、芸当、調子、言い回しなどの意味が派生しました。ランボーは地元の歌などからヒントを得ているように思えます。2行目の末尾は原文はコロン(:)で終わり、次の3・4行がこのお囃子に当たると考えられます。直訳すると、「波と草木( flore 植物群)にすぎないが、それは君の家族だ」となります。「波 onde 」は、たとえば広場に集まった人の波などにも使われます。ここでは、「最も高い「塔」の歌」の第4節のように、波打つほど繁った草地をイメージして訳しました。
ここに描かれたのは、初期詩編時代までの田舎でのランボーの生活でしょう。宗教的、道徳的な、口うるさい母親が登場します。「ドイツ口調」は、母親のなまりのことを言っているのでしょうか。ランボーの故郷、アルデンヌがベルギー、ドイツに近い地方であり、ランボーにもアルデンヌなまりがあったと書かれています。ランボーという名前がドイツから来たことを示しているという説を読んだことがあります。『地獄での一季節』の「悪い血筋」の第2節には、祖先の足跡を思わせる記述「おれは土百姓で……ドイツの夜空の下に露営したのかも知れない。」が書かれています。小言を言われたランボーは、夢想の中に逃げ込みます。
写真:秋山まほこ(秋山まほこ人形作品集「Ange」1991年トレヴィル発行)
解読:門司 邦雄
掲載:2002年3月30日、2002年7月8日、2003年4月18日、7月10日、2006年5月20日、20066月29日、2014年1月15日リンク更新
<< 朝の名案 index 飢えの祭 >>